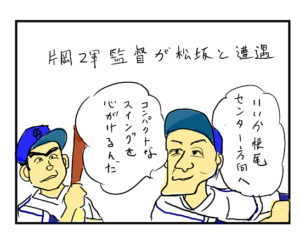20年ぶりの優勝を振り返る(1974年)
その日の中日球場は、熱気と歓声が満ち溢れていました。スタンドを埋め尽くしたファンの興奮は極みに達していました。
1974年(昭和49年)10月12日、午後8時8分。
大洋ホエールズの山下大輔のサードライナーを島谷金二が軽くジャンプしてグラブに収めた瞬間。それを見届けたマウンドの星野仙一が、捕手木俣達彦にかけより、通常なら投手がキャッチャーに抱き着くところを、捕手木俣が星野に抱き着く形となり、星野が木俣を抱え上げました。

マスクをかぶったままの木俣
しかも、木俣はマスクをかぶったまま。そこへ、高木守道、島谷、谷沢健一がかけよる。与那嶺監督、近藤ヘッドコーチがマウンドに集まって監督の胴上げが始まる。さらにファンがフェンスを乗り越えて、選手めがけて、グランドに降りて来る。与那嶺監督は、ほんの2.3回宙に浮きましたが、ファンにかき消され、あとはもう何が何だか分からない、選手がファンに胴上げされている。
私は小学生の低学年で、この瞬間はテレビで見ていました。 しばらくすると、外野のスタンド方向から、神輿が入ってきました。なぜかこの神輿の記憶があります。あと、マーチンがファンに帽子を取られ、頭の「禿げ」がテレビに映り、選手達がおのおの、ベンチに下がって行きました。
監督の与那嶺は選手達に、「巨人だけには負けるわけにはいかない」と選手達に繰り返しました。選手達への意識改革を行い、実際に4年連続で負け越していた相手に、72年、73年と2年連続で勝ち越していました。
ウォーリー与那嶺は、元々ジャイアンツの選手でした。負け犬根性だけは古巣に見せたくはありませんでした。
優勝チームには、絶対的なエース、巨人のONの様なスターがいます。しかし、ドラゴンズには、それほどのスターはいませんでした。「スター無き優勝」と言われ、まさにチームワークが生んだ優勝でした。
与那嶺はいつも、マスコミに語っていました。「コーチ、選手、みんなが一生懸命やってくれた結果」どんな質問をされようが「みんなの力で勝ち取った優勝」と。
前カードヤクルト戦の死闘
9月の時点で2位のジャイアンツに5ゲーム差をつけていましたが、その後、1進1退。
マジックは点灯していましたが、神宮でのヤクルト戦に連敗し、その後の試合に1敗するとマジック消滅の危機となりました。
この大事な試合は終盤まで接戦で2-3。1点ビハインドの苦しい展開。そして9回の表2死で三塁に木俣達彦を置き、打者は高木守道でマウンドには抑えの倉田。執念の打球が、しぶとくレフトの前に転がっていく。土壇場で値千金の同点となりました。
そして、マウンドにはなんと、8人目の投手星野仙一が登りました。
緊張極限状態のマウンド
今までにない、ものすごい顔つきでマウンドに上がっていました。気持ちが高ぶっているのではなく、緊張からの表情で、実際に膝がガクガク震えていました。
星野仙一は優勝後の話の中で、もっとも印象に残る試合に、このヤクルト戦を上げています。
その証拠に、次節の優勝を決めた大洋戦は、ダブルヘッダーでしたが、選手達から硬さも不安も消えていました。
この試合の第1試合で飛び出した島谷とマーチンの2本のツーランホームランで先制し、9-2の大差で勝利をかざると、続く第1試合は6-1の完勝で優勝決定となりました。
星野仙一は「優勝して嬉しかったと言うよりも、優勝してホットした、肩の荷が下りた」と。それほど、地元、名古屋の中日ファンの熱狂は凄かったのです。街中ではいたるところから「燃えよドラゴンズ」の応援歌が流れ、地元、テレビ、ラジオでドラゴンズの話題が取り上げられていました。
ファンが20年間この日を待ち望んで、夢がかなった瞬間でした。
青竜研究会